版画を作り始めてもう何年にもなりますが、その間、先輩の職人さんたちからこんな忠告を何度も受けてきました。「何にでも手を出すのは止めて、彫なら彫に専念するんだよ。そして、他のことは別の人たちに任せたらいいのさ。」でも、実際に彫と摺の作業が必要になると、そんな忠告は無視してきました。作品は「自分の手で」作りたいと心底思っているからです。
もちろん、道具や材料は他の職人さんたちに依存しなくてはなりませんが、近頃は紙の供給に関して不安がでてきました。手漉き和紙はそのまま使うことはできず、摺る前にドーサ(ニカワの混合体)引きを必要とします。これを専門に引き受ける職人さんが、紙を作る人と摺師の間に必要なのです。
現在、伝統木版画を摺る人達がこの作業を依頼できる職人は、たった一人しかいません。しかも、弟子を持たないこの人が引退する日は迫ってきているという実情です。もしこの職人さんが「もう刷毛は持たないことにするよ」と宣言すれば、私のような立場にある者は途方に暮れることになります。仕事に必要な和紙にドーサ引きが出来ないことになるのですから。
それで最近は、ただ手をこまねいてこの日の来るのを待つのでなく、作品制作に欠かせないこの技術を身につけようと、自分でこの作業を始めることにしました。
一番の難問は変動する要素がたくさんあることです。ニカワとミョウバンが正しい割合で混合された溶液を作る「方法」は、天候・湿度・紙の状態・作品による要求などによって、大きく左右されるのです。経験豊富な職人なら、こういったことを瞬時に踏まえて作業ができるのですが、初心者はひたすら、「常識」範囲を逸脱しなければ迷走する心配はないだろうと期待するのみです。
次の問題は、ほぼ解決不可能なもので、必要な道具が手に入らないということです。私は都内にある何軒もの刷毛屋に問い合わせましたが、返ってきた答えは決まって同じでした。「残念ですが、そういった刷毛はもう作っていません。」仕方なく、この作業には遥かに小さすぎる刷毛で間に合わせることになりました。
次のページにある写真で、実際に行った作業の経過をご覧になることができます。まだ自信が付いたとは言えませんが、使用できるまずまずの結果は得られました。現在進行中の「美の謎」シリーズの最新作品は、私がこうしてドーサ引きをした和紙で作っています。
今後も自分でドーサ引きをすると、作品制作に掛かる時間と労力が大幅に増加しますが、現実問題として他に選択の余地がないのです。和紙や版木や絵の具など、他の必需品については、後継者がいるのでなんとかなると楽観しています。
Overview of the process ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A few more points ...
|
|
|
|
|
|

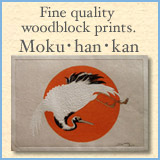


 ニカワとミョウバンの混合液を湯煎でゆっくり溶かす。
ニカワとミョウバンの混合液を湯煎でゆっくり溶かす。 漉して、不純物や塊を取り除く。
漉して、不純物や塊を取り除く。 安定した温度を保つために小さな温度計が活躍。
安定した温度を保つために小さな温度計が活躍。 ここが最も難関。紙一面にむらなくドーサを引く。
ここが最も難関。紙一面にむらなくドーサを引く。 皺のできないように紙を吊り下げる道具を作った。
皺のできないように紙を吊り下げる道具を作った。 重要!ゆっくり乾燥させないと、むときに紙がよれる。
重要!ゆっくり乾燥させないと、むときに紙がよれる。 やっと手に入れた刷毛は幅一尺なので、1枚の紙にひと刷毛でドーサ引きするには狭すぎます。仕方なく紙を半分に切り、作業時間は2倍になりました。(もちろん、紙は小さい方が初心者には「楽」ですよね!)
やっと手に入れた刷毛は幅一尺なので、1枚の紙にひと刷毛でドーサ引きするには狭すぎます。仕方なく紙を半分に切り、作業時間は2倍になりました。(もちろん、紙は小さい方が初心者には「楽」ですよね!) 地元にある板金屋さんは、すべて店じまい。仕方なく、自分で刷毛の幅に合わせて容器を作りました。湯煎用なので、水を入れたホットプレートの中にピッタリ漬かるようにしました。
地元にある板金屋さんは、すべて店じまい。仕方なく、自分で刷毛の幅に合わせて容器を作りました。湯煎用なので、水を入れたホットプレートの中にピッタリ漬かるようにしました。 これは自慢できる妙案です。濡れて柔らかくなっている和紙を吊り下げるのはとても難しいのですが、挟む部分が滑らかになっているランジェリー用の洗濯バサミを利用して、たくさんのハンガーを作りました。この行程に関しては問題なしです!
これは自慢できる妙案です。濡れて柔らかくなっている和紙を吊り下げるのはとても難しいのですが、挟む部分が滑らかになっているランジェリー用の洗濯バサミを利用して、たくさんのハンガーを作りました。この行程に関しては問題なしです!
コメントする