掛軸制作のあらまし
「展示会報告」のところで、昨年の掛軸が展示会までに完了しなかった旨を説明しました。でも、それはほんの数ヶ月前のことです。現在はすべて終わって、予約なさった方達は作品を手にしていらっしゃいますし、私のバレンは、次の企画が始まって出番が来るまで休憩中になっています。
作品の制作は1年掛かりでしたので、その間、予約をして御待ち下さっておられる方達に、制作の進行状況を数回お送りしました。掛軸の制作工程を知るのは、他の方達にも面白いのではと考え、報告の一部を御紹介します。
* * *
|
 今回の掛軸は、とても大きな作品ですから、用いる版木はとても高価です。自作の専用摺台を使えば、細かな彫のある小さな版木も使うことができます。 今回の掛軸は、とても大きな作品ですから、用いる版木はとても高価です。自作の専用摺台を使えば、細かな彫のある小さな版木も使うことができます。
|
|
 主要な墨線だけでなく、模様もすべてなぞって版下を作ってゆきます。… 精度のよい写真を複写して、それを、私のパソコンに取り込みました。… 専用のタブレットの上に高感度の「ペン」で画いてゆくます。… タブレットとペンの間には、恐ろしく精巧な感度があります。ですから、実際の筆で画いたような線を作ることが可能です。 主要な墨線だけでなく、模様もすべてなぞって版下を作ってゆきます。… 精度のよい写真を複写して、それを、私のパソコンに取り込みました。… 専用のタブレットの上に高感度の「ペン」で画いてゆくます。… タブレットとペンの間には、恐ろしく精巧な感度があります。ですから、実際の筆で画いたような線を作ることが可能です。
|
|
 でき上がった版下の部分です。必要となる何枚もの版木を彫るためには、原画にあるどのような細部も画き入れなくてはなりません。 でき上がった版下の部分です。必要となる何枚もの版木を彫るためには、原画にあるどのような細部も画き入れなくてはなりません。
|
|
 版下画きが完了したら、自分が用意した特別な紙に、その複製を作ります。 版下画きが完了したら、自分が用意した特別な紙に、その複製を作ります。
次の作業は長い色分けの行程で、どの部分を彫りどの部分を残すかを決めます。
|
|
 その次は、彫を始めるために版下を版木に貼付ける作業です。その後私は、裏の層となっている紙を剥がし、版木の表面に薄い雁皮だけが残るようにします。 その次は、彫を始めるために版下を版木に貼付ける作業です。その後私は、裏の層となっている紙を剥がし、版木の表面に薄い雁皮だけが残るようにします。
|
|
 この写真は、私のウェブカメラで捉えたものです。作業台を見下ろす位置にビデオカメラを取り付け、インターネットを通じて、私の作業をライブで公開しています。 この写真は、私のウェブカメラで捉えたものです。作業台を見下ろす位置にビデオカメラを取り付け、インターネットを通じて、私の作業をライブで公開しています。
|
|
 これは、模様を摺る版のひとつです。まだ彫は完了していず、小さな四角は全て取り除かなくてはなりません... が、四角の中央にある点は、どれも残さなくてはならないのです! これは、模様を摺る版のひとつです。まだ彫は完了していず、小さな四角は全て取り除かなくてはなりません... が、四角の中央にある点は、どれも残さなくてはならないのです!
|
|
 版木の数は13枚です。でも、摺る領域の数は別なのです。今回は、非常にたくさんの色を使うので、ひとつの版木に違う色を一緒に彫ることができます。 版木の数は13枚です。でも、摺る領域の数は別なのです。今回は、非常にたくさんの色を使うので、ひとつの版木に違う色を一緒に彫ることができます。
色分けを記した手元の資料では、唇のように小さな部分から背景のように広い範囲まで、42色の領域があることになっています。
|
|
 材は生きているので、常に見当を調整しなくてはなりません。
それで、しっかりとした材質のマイラープラスチックを利用するつもりです。 材は生きているので、常に見当を調整しなくてはなりません。
それで、しっかりとした材質のマイラープラスチックを利用するつもりです。
色版を1枚ずつ置いて、透明なマイラー上の輪郭線を見ながら詰め木を入れて、版木の位置を調整するのです。
|
|
 紙が反るように持ち、箱の中の和紙床から版木の上まで手前に移動します。想像できるかと思いますが、大きくて柔らかい紙が湿った状態ですから、思い通りに動かすことはとても難しいのです。はらりと、うっかり下に降りてしまうようなことがないよう、紙の端から端までしっかりと張った状態で移動します。 紙が反るように持ち、箱の中の和紙床から版木の上まで手前に移動します。想像できるかと思いますが、大きくて柔らかい紙が湿った状態ですから、思い通りに動かすことはとても難しいのです。はらりと、うっかり下に降りてしまうようなことがないよう、紙の端から端までしっかりと張った状態で移動します。
|
|
 今までは、比較的小さな作品を制作していたので、これ程大きくなると新たな問題がたくさん出てきて、作業は遅々として進まない状況になってしまいました。 今までは、比較的小さな作品を制作していたので、これ程大きくなると新たな問題がたくさん出てきて、作業は遅々として進まない状況になってしまいました。
和紙は湿度によって伸縮するので、小さな部分を摺った後には湿り気を加え、広い領域を摺った後にはそれを取り除きます。また、乾燥した日には加湿し雨の日には除湿 ...
|
|
 摺が終わると、掛軸として表装できる薄さにしなくてはなりません。厚すぎると、皺ができやすくなり、巻いた時に版画を痛めてしてしまいます。 摺が終わると、掛軸として表装できる薄さにしなくてはなりません。厚すぎると、皺ができやすくなり、巻いた時に版画を痛めてしてしまいます。
まず、角の部分の繊維を逆立てます。紙が2枚に剥がれ始めたら、裏半分がはっきり分かれるまで剥がします。
|
|
 最近の表装工房は、接着剤や大型のプレス機械を使うようになっていますが、私としては、のりを用いて自然乾燥するという、伝統方式で表装してほしかったのです。ここにある写真は、中国にいる表装職人の王建方さんに作品の状態を調べてもらい、相談をしているところです。私達は、彼が表装した商品をたくさん見てその技術を高く評価し、彼にお願いすることにしました。 最近の表装工房は、接着剤や大型のプレス機械を使うようになっていますが、私としては、のりを用いて自然乾燥するという、伝統方式で表装してほしかったのです。ここにある写真は、中国にいる表装職人の王建方さんに作品の状態を調べてもらい、相談をしているところです。私達は、彼が表装した商品をたくさん見てその技術を高く評価し、彼にお願いすることにしました。
|
|
 プロの書家でもある、収集家の田内様の御陰で、美しく題が書かれた桐箱に入れて皆様にお届けすることができました。 プロの書家でもある、収集家の田内様の御陰で、美しく題が書かれた桐箱に入れて皆様にお届けすることができました。
|
|
 長くて密度の濃い企画でしたが、やっと完成にこぎ着ける事ができました。かつてないほどの習練となり、しかも面白味の尽きない経験でした。1年前と較べると、遥かに経験を積んだ摺師になった気がします。 長くて密度の濃い企画でしたが、やっと完成にこぎ着ける事ができました。かつてないほどの習練となり、しかも面白味の尽きない経験でした。1年前と較べると、遥かに経験を積んだ摺師になった気がします。
|
* * *
次のページに移って先をお読みいただく前に、お知らせがあります。掛軸は、注文数よりも多少余分に制作してありますので、作品を御希望の方は連絡をお願いいたします。

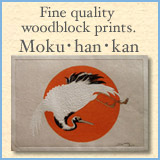

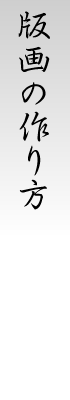
 今回の掛軸は、とても大きな作品ですから、用いる版木はとても高価です。自作の専用摺台を使えば、細かな彫のある小さな版木も使うことができます。
今回の掛軸は、とても大きな作品ですから、用いる版木はとても高価です。自作の専用摺台を使えば、細かな彫のある小さな版木も使うことができます。
 主要な墨線だけでなく、模様もすべてなぞって版下を作ってゆきます。… 精度のよい写真を複写して、それを、私のパソコンに取り込みました。… 専用のタブレットの上に高感度の「ペン」で画いてゆくます。… タブレットとペンの間には、恐ろしく精巧な感度があります。ですから、実際の筆で画いたような線を作ることが可能です。
主要な墨線だけでなく、模様もすべてなぞって版下を作ってゆきます。… 精度のよい写真を複写して、それを、私のパソコンに取り込みました。… 専用のタブレットの上に高感度の「ペン」で画いてゆくます。… タブレットとペンの間には、恐ろしく精巧な感度があります。ですから、実際の筆で画いたような線を作ることが可能です。 でき上がった版下の部分です。必要となる何枚もの版木を彫るためには、原画にあるどのような細部も画き入れなくてはなりません。
でき上がった版下の部分です。必要となる何枚もの版木を彫るためには、原画にあるどのような細部も画き入れなくてはなりません。 版下画きが完了したら、自分が用意した特別な紙に、その複製を作ります。
版下画きが完了したら、自分が用意した特別な紙に、その複製を作ります。 その次は、彫を始めるために版下を版木に貼付ける作業です。その後私は、裏の層となっている紙を剥がし、版木の表面に薄い雁皮だけが残るようにします。
その次は、彫を始めるために版下を版木に貼付ける作業です。その後私は、裏の層となっている紙を剥がし、版木の表面に薄い雁皮だけが残るようにします。 この写真は、私のウェブカメラで捉えたものです。作業台を見下ろす位置にビデオカメラを取り付け、インターネットを通じて、私の作業をライブで公開しています。
この写真は、私のウェブカメラで捉えたものです。作業台を見下ろす位置にビデオカメラを取り付け、インターネットを通じて、私の作業をライブで公開しています。 これは、模様を摺る版のひとつです。まだ彫は完了していず、小さな四角は全て取り除かなくてはなりません... が、四角の中央にある点は、どれも残さなくてはならないのです!
これは、模様を摺る版のひとつです。まだ彫は完了していず、小さな四角は全て取り除かなくてはなりません... が、四角の中央にある点は、どれも残さなくてはならないのです! 版木の数は13枚です。でも、摺る領域の数は別なのです。今回は、非常にたくさんの色を使うので、ひとつの版木に違う色を一緒に彫ることができます。
版木の数は13枚です。でも、摺る領域の数は別なのです。今回は、非常にたくさんの色を使うので、ひとつの版木に違う色を一緒に彫ることができます。 材は生きているので、常に見当を調整しなくてはなりません。
それで、しっかりとした材質のマイラープラスチックを利用するつもりです。
材は生きているので、常に見当を調整しなくてはなりません。
それで、しっかりとした材質のマイラープラスチックを利用するつもりです。 紙が反るように持ち、箱の中の和紙床から版木の上まで手前に移動します。想像できるかと思いますが、大きくて柔らかい紙が湿った状態ですから、思い通りに動かすことはとても難しいのです。はらりと、うっかり下に降りてしまうようなことがないよう、紙の端から端までしっかりと張った状態で移動します。
紙が反るように持ち、箱の中の和紙床から版木の上まで手前に移動します。想像できるかと思いますが、大きくて柔らかい紙が湿った状態ですから、思い通りに動かすことはとても難しいのです。はらりと、うっかり下に降りてしまうようなことがないよう、紙の端から端までしっかりと張った状態で移動します。 今までは、比較的小さな作品を制作していたので、これ程大きくなると新たな問題がたくさん出てきて、作業は遅々として進まない状況になってしまいました。
今までは、比較的小さな作品を制作していたので、これ程大きくなると新たな問題がたくさん出てきて、作業は遅々として進まない状況になってしまいました。 摺が終わると、掛軸として表装できる薄さにしなくてはなりません。厚すぎると、皺ができやすくなり、巻いた時に版画を痛めてしてしまいます。
摺が終わると、掛軸として表装できる薄さにしなくてはなりません。厚すぎると、皺ができやすくなり、巻いた時に版画を痛めてしてしまいます。 最近の表装工房は、接着剤や大型のプレス機械を使うようになっていますが、私としては、のりを用いて自然乾燥するという、伝統方式で表装してほしかったのです。ここにある写真は、中国にいる表装職人の王建方さんに作品の状態を調べてもらい、相談をしているところです。私達は、彼が表装した商品をたくさん見てその技術を高く評価し、彼にお願いすることにしました。
最近の表装工房は、接着剤や大型のプレス機械を使うようになっていますが、私としては、のりを用いて自然乾燥するという、伝統方式で表装してほしかったのです。ここにある写真は、中国にいる表装職人の王建方さんに作品の状態を調べてもらい、相談をしているところです。私達は、彼が表装した商品をたくさん見てその技術を高く評価し、彼にお願いすることにしました。 プロの書家でもある、収集家の田内様の御陰で、美しく題が書かれた桐箱に入れて皆様にお届けすることができました。
プロの書家でもある、収集家の田内様の御陰で、美しく題が書かれた桐箱に入れて皆様にお届けすることができました。 長くて密度の濃い企画でしたが、やっと完成にこぎ着ける事ができました。かつてないほどの習練となり、しかも面白味の尽きない経験でした。1年前と較べると、遥かに経験を積んだ摺師になった気がします。
長くて密度の濃い企画でしたが、やっと完成にこぎ着ける事ができました。かつてないほどの習練となり、しかも面白味の尽きない経験でした。1年前と較べると、遥かに経験を積んだ摺師になった気がします。
コメントする