毎年の展示会では、私の仕事について書かれた記事の切り抜きを、毎年追加して展示してきました。自分の作品を一般に公開するようになって16年が過ぎ、日本国内におけるメディア業界は私の活動についてかなり好意的な反応を示してきているので、展示量はどんどん増えています。
記事として取り上げられるのは、外国人が日本の伝統文化に取り組んでいるから、というのもある程度は理由でしょう。でも私としては、同じ企画をしたのが日本人であったとしても記事にする価値があるとみなされた、と考えたいのです。
毎回、展示会が近くなると、記事として載せてもらうための宣伝用資料をたくさん送付しますが、それとは関係なく、編集者がどこからともなく私のしていることについての情報を得て、それが使えると判断し連絡してくる場合もあります。でも、それがテレビ番組の場合は、慎重になります。というのは、静かに考えながら行う私の仕事とは、控えめにみても、およそ懸け離れた放送目的で依頼してくることもあるからです。
私の作品を気に入ってくださる人達の中には、ことに外国に住んでいる方の場合、私のことが書かれた記事を読んだり出演した番組を見る機会のなかった方もいらっしゃることと思い、ここに紹介することにしました。昨年中にメディアで取り上げられた中から...。
週間求人情報雑誌:ガテン、2004年6月号-- 「和の職人になった外国人」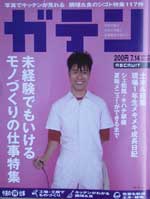 この雑誌に取り上げられたのは、これで3回目です。この雑誌は、仕事を探している人達に求人情報を提供するのが主な目的ですが、様々な仕事に従事している人達を分かりやすく紹介してもいます。ところが、この号に目を通してみたら、版画職人の募集はなかったんです!
この雑誌に取り上げられたのは、これで3回目です。この雑誌は、仕事を探している人達に求人情報を提供するのが主な目的ですが、様々な仕事に従事している人達を分かりやすく紹介してもいます。ところが、この号に目を通してみたら、版画職人の募集はなかったんです!
抜粋:デービッドの言葉より 「私の目も肥えてきます。すると、これまでの自分の作品がジャンクになる。今日のベストは明日のジャンク。でも、人生最後までトライ。今日より少しいいものを作る。一つのことをずっとやり続けると、とても上手になる。それがハッピーです」
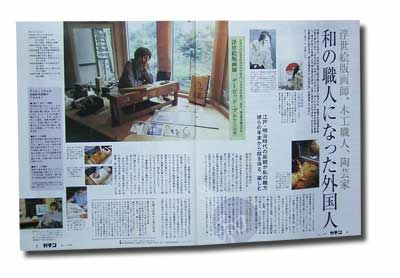 機関誌:コンセンサス、2004年9~10月号 --「木版画職人デービッド・ブルさん」
機関誌:コンセンサス、2004年9~10月号 --「木版画職人デービッド・ブルさん」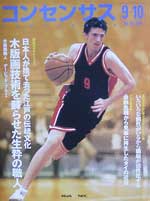 これは、NECが発行している機関紙です。彼らの事業内容と私のしている事は、ほとんど関連性がありませんが、私の記事が掲載されたのは「創造のダイナミクス」というコラムで、自分で道を切り開くような生き方をする人達を取り上げています。
これは、NECが発行している機関紙です。彼らの事業内容と私のしている事は、ほとんど関連性がありませんが、私の記事が掲載されたのは「創造のダイナミクス」というコラムで、自分で道を切り開くような生き方をする人達を取り上げています。
抜粋: 「デービッドさんは、江戸時代から明治期の日本の木版画技術が古今東西で最高峰だと信じて疑わない。」
デービッド:『日本の木版画は中国や韓国の伝統とはまったく技法が違う。ヨーロッパにも技術はあったが日本の職人にはとうていおよびません。日本の木版画は日本で生まれた日本独自の技術であり、本当のメイド・イン・ジャパンなんです』
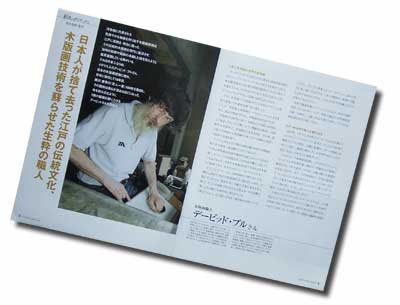 What's Up?、2004年5月号-- "I am a Craftsman, not an Artist"「私は職人、芸術家ではない」
What's Up?、2004年5月号-- "I am a Craftsman, not an Artist"「私は職人、芸術家ではない」 これは雑誌でなく、高校生用の英語の副教材です。伝統文化の職人として生計を立てることは可能なのだ、ということを若い人達に伝えることは大切なことだと思い、喜んで編集者に協力しました。
これは雑誌でなく、高校生用の英語の副教材です。伝統文化の職人として生計を立てることは可能なのだ、ということを若い人達に伝えることは大切なことだと思い、喜んで編集者に協力しました。
抜粋: "David moved to Japan to study the skills to produce ukiyo-e when he was in his mid-thirties. He struggled to gain the traditional skills for a long time. Eventually, however, with the help of many Japanese craftsmen, he mastered the skills. Now he enjoys reproducing ukiyo-e. He has finally made his dream come true in Japan."
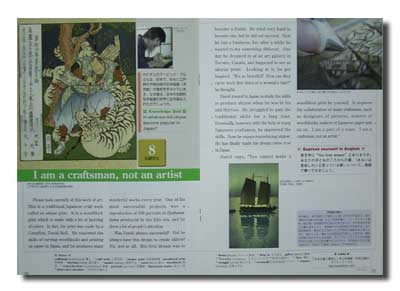 テレビ東京、2004年10月14日放映 -- 「たけしの誰でもピカソ」
テレビ東京、2004年10月14日放映 -- 「たけしの誰でもピカソ」ゴールデンタイムに放映されるこういった種類の番組は、手早く編集して限られた時間内にできるだけ多くの情報を詰め込むのが普通です。ですから、結果として深みのある内容にならなくても、幅広い層の人達が私の仕事についてちょっとでも知る機会となれば嬉しいと思っています。

Q. 「やはり日本の伝統文化を残していきたいですか?」
A. 「あんまりそういった考えは、ありません。なぜやっているかと言うと、自分が好きです。... 物を作る人と物を使う人が両方いると、伝統が自然に続くことになります。それが一番いい方法だと思います」
NHK教育テレビ、2004年11月放映 -- 「みんな生きている」たっぷり時間をかけて制作された、15分間のミニドキュメンタリー形式の番組です。NHKは実に用意周到で、しかもたくさんの時間をかけるので、私としては費やせる時間がほぼ限界でした。でも放映されてみると、時間をかけただけのことはあったのだとよく分かったのです。視聴者からの反応は好意的で、とても喜ばれたようです。

「人が作ったものとは信じられないですね。繊細な線の彫り、微妙な色、美しい和紙、うそみたいです。私の国にも木版画はありますが、全然違います」
「(彫の線は)1本1本がほんとうにスムーズできれいじゃないとおかしい。丁寧過ぎても、おかしくなります。サ〜ササッと彫ると、自然な線が生まれるんです」

ナレーション: 「百年前の技に挑戦していると、今となっては、どうやって彫ったのかわからないことがあります。たとえば、この筆で画いたような掠れた線。こんな時は昔の本に頼ります」
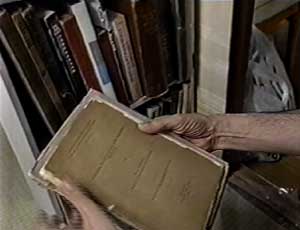
デービッド: 「この棚の中にあるのは、私の先生ですよ。明治時代の木版画のプロセスが書いてあります。色々と細かい事が書かれてます」
ナレーション:「本には、掠れという技があった事は紹介されていました。でも、どういう彫り方なのかは書かれていません。残された道はひとつ、自分で試してみるしかありません。...中略 ... 知らない技に挑むのはとても楽しい、とデービッドさんは言います」

紙面の都合上、今回はこの程度にしておきましょう。今度は、どんな問い合わせの電話が掛かって来るでしょうか。そして、来年はどんな報告が書けるのでしょうか?

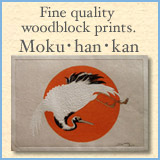



コメントする